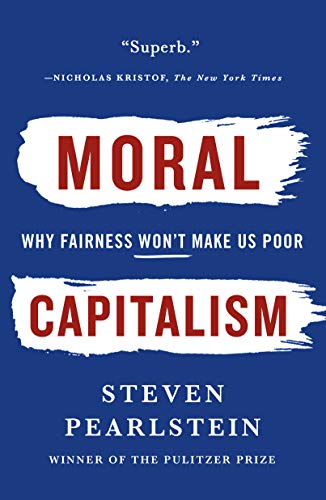ティム・オライリー御大が O'Reilly Radar ブログに長文エントリを寄稿している。URL を見れば分かるが、当初のタイトルは「なんでイーロン・マスクはそんなにリッチなのか」だったが、ちょっと釣りタイトル過ぎると反省したのか、穏当なタイトルに変わっている。性格が悪いワタシは、その当初のタイトルを改めて掲げて、その内容を大まかにまとめてみたい。
今年のはじめ、短い間ながらもイーロン・マスクは世界でもっともリッチな人になった。彼の会社テスラの株価が上がったおかげで、一時は2000億ドルを超えた彼の純資産は、今では「たった」1550億ドルばかしに落ち着いている。
こんなことをもたらす経済の仕組み、具体的には何がよくて何が危険か理解するのが、我々の社会を引き裂かんとする激しい不平等に対処するのに欠かせないとオライリーは考えているわけだ。
賭博経済(betting economy)対事業経済(operating economy)
イーロン・マスクが資産をむちゃんこ増やしたニュースを受け、バーニー・サンダースは「2020年3月18日、イーロン・マスクの資産は245億ドル。2021年1月9日、イーロン・マスクの資産は2090億ドル。一方、アメリカの最低賃金は2009年も2021年も時給7.25ドル」とイヤミをツイートした。
1979年以降の生産性向上を反映するなら最低賃金は現在24ドルになってるはずで、最低賃金が上がってないのに怒るバーニー・サンダースは正しいが、イーロン・マスクの富がテスラの労働者を食い物にした結果と見るのは間違っているとオライリーは予防線を張る。
イーロン・マスクはテスラの利益を搾取するぼったくり男爵ではない。というか、テスラはずっと利益を出してなかったし、2020年にしても7.21億ドルの利益は、売上高の2%強に過ぎず、全然大したものじゃない。
マスクが勝ったのは株式市場における美人投票なのだ。理論的には、株価は継続的な利益とキャッシュフローを生み出す企業価値の反映だが、実際にはその企業の現状と無関係に乱高下することがある。
なんでイーロン・マスクはそんなにリッチなのか? それは人々が彼に賭けているからだ。しかも宝くじなど一般の賭けと違い、株式市場ではレースが終わる前に賞金を現金化できてしまう。
これがアメリカにおける不平等の最大の要因の一つであり、コロナ禍で(庶民が苦しむ一方で)金持ちが大いに資産を増やした理由でもある。
ここまで読んで、どうしても以前解説したオライリーの文章を思い出してしまう。betting economy と operating economy の対比はこの文章にも出てくるが、このエントリに対する反応にも以下のようなものがあった。
ティム・オライリーが「シリコンバレーの終焉」について長文を書いていたのでまとめておく - YAMDAS現更新履歴
- [あとで読む]
イーロン・マスクを気候変動億万長者の例としてあげてるようだけど、テスラはbetting economyの代表株だと思うのだが。
2021/04/21 00:42
イーロン・マスクを気候変動億万長者の例としてあげてるようだけど、テスラはbetting economyの代表株だと思うのだが。 - doas1999 のブックマーク / はてなブックマーク
確かにワタシは、この文章でオライリーはテスラを operating economy と見なしていると読んだのだが、上に引用したように反対だろと見る人もいるだろうし、今回の文章をここまで読んだだけでは、オライリーもテスラ(というかイーロン・マスク)を betting economy そのものと思ってるんじゃないのと読めてしまう。どうなのか?
確率はどれくらい?
株式市場がレース中に賭け金を現金化できるものなら、それなら何をもってレースは終了なのか? 起業家や初期ステージの投資家にとっては株式公開が一種のゴールだし、買収や事業停止もまたしかり。一方で、企業の利益で投資を回収する時点をもって「レースの終わり」とも言える。
例えば、100万ドルかけて会社を買い、その会社が年間10万ドルの利益を出すなら、投資額は10年で回収できる。もちろん、今日得られる1ドルと10年後、20年後に得られる1ドルは同価値ではないが、単純化してしまえば、株とはその会社の将来の利益と現在の価値に対する請求権と言える。
成長率も企業価値に影響を与える。株を買ったときにその企業のライフサイクルのどの段階にあるかでその所有価値は決まる。例えば、今の Apple などビッグテックが5万ドルの利益しかあげてなかったころに運よく株を買えたなら、わずかな投資であっても長期保有で億万長者になれるかもしれない。テスラもそうした企業になれるかもしれないが、既にテスラの株式市場での評価は十分高いので、その「未来を買う」チャンスは過ぎ去っている可能性が高い。
テスラの PER(株価収益率)は1396で(注意:リンク先の数字は、当然オライリーが原文を書いたときとかなり異なる)、今テスラの株を買ったら、その資金を利益分配で取り戻すのに1400年近くかかることになる。最近テスラの収益は上がり、また株価もかなり下がっているので、今ならおよそ600年待つだけで済むよ。
もちろんテスラが自動車産業で圧倒的な強さを発揮して利益を増やす可能性はあるが、Big Market Delusion: Electric Vehicles という分析によると、電気自動車メーカーは売上も利益も少ない上に、将来的に競争が激化する可能性があるにもかかわらず、既に既存の自動車産業とほぼ同等の評価を受けている。
ならなんで投資家はテスラの株を買うのか? 簡単に言えば、テスラ株はもっと高い値段で誰かに売れると考えるからだ。17世紀のオランダのチューリップ・バブルを引き合いに出すまでもなく、そうしたバブルはいずれは崩壊する。
この賭博経済は、合理的な範囲内であれば良いもので、未来への投機的投資はいろんな新製品、生産性や生活水準の向上をもたらす。テスラは再生可能エネルギーのゴールドラッシュをもたらしたが、これは気候変動の問題を考える上で重要なことだ。賭博の熱狂は(インターネットの構築がそうだったように)有益な集団的フィクションとなりえるし、革命的な新技術が受け入れられるサイクルでバブルは自然な現象である。
ここでオライリーは賭博経済が道を踏み外した例として、WeWork と Clubhouse を挙げていて、シリコンバレーには、利益も出さず、ビジネスモデルも機能せず、収益への道筋もないのに時価総額が数十億ドルの企業が溢れている、と苦言を呈している。オライリーさん、Clubhouse は評価できませんか(笑)。関係ないですが、ワタシも先月末に Clubhouse のアカウントを削除しました。
そしてオライリーは、前回同様ケインズの『一般理論』から、「事業の安定した流れがあれば、その上のあぶくとして投機家がいても害はありません。でも事業のほうが投機の大渦におけるあぶくになってしまうと、その立場は深刻なものです。ある国の資本発展がカジノ活動の副産物になってしまったら、その仕事はたぶんまずい出来となるでしょう」のくだりを引用し、ここ数十年、ドットコムの崩壊、サブプライムローンの崩壊、現在のシリコンバレーの「ユニコーン」バブル、と経済全体が投機の渦に巻き込まれるのを目の当たりにしてきたと書く。
なぜバブルが重要なのか
賭博経済のプレイヤーは不釣り合いに裕福なので、負けることを恐れていない。株式市場の価値の半分以上をアメリカ人の上位1%が保有している。アメリカ人の下位50%は、株式市場のたった0.7%しか保有していないのにね。
地元の個人経営の会社なら、1ドルの利益はそのまま1ドルの価値だが、テスラは1ドルの利益で600ドルの株式市場価値を引き出す。このバブルこそが、現代の経済において、金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏になる理由の一つである。金持ちと貧乏人は、現実には別のルールで仕切られる別の経済に生きているのだ。金持ちの多くは、資産が金融化され、賭博経済に参加でき、何十年分もの将来の収益を反映した株価で評価される、つまり未来から無利子の巨額融資を受けられる「スーパーマネー」の世界に住んでいるのだ。
さて、ここまで読んだところで、オライリーが改題したタイトル「Two economies. Two sets of rules.」の意味、そして、その下に添えられた「イーロン・マスクはスーパーマンではない。だけど彼には「スーパーマネー」がある」という文の意味が分かるわけですな。
イーロン・マスクは世界を変える会社を二つも作り上げた(テスラとスペースX)。でもいくらなんでも富が多すぎやしないか? バーニー・サンダースが「億万長者は存在すべきではない」と言ったとき、マーク・ザッカーバーグは蓄積される富の中には理不尽なものもあると認めたが、何十億ドルもの報酬がないと起業家がイノベーションを起こさなくなるという考え方は、悪質な幻想である。
ならばどうすべきか
富裕層に税金を課し、その富を再分配すれば問題は解決すると思うかもしれない。実際、1970年代まで、つまりはレーガノミクス登場前は、所得税の累進課税率が90%に達していたため、富の再分配と幅広い中産階級の形成がうまくいった。オライリーはそれはそれとして、幻の富を生み出している「賭博経済」にも歯止めをかける必要があるのではないかと訴える。
不平等を解消するには、「スーパーマネー」が経済で果たしている役割を認識しないといけない。それなしに増税しても効果は薄いというわけ。
しかし、政府がスーパーマネーに甘いという現実がある。世界中の中央銀行は、インフレを引き起こさずに成長率を維持するため、サブプライムローン問題以降、刷ったお金を世界中にばらまく「量的緩和」によってこれを実現しようとしている。それにより金利は低く保たれ、理論的には実体経済への投資が活発になり、雇用や工場やインフラに資金が供給されるはずだった。が、現実はそうはならず、あまりにも多くのお金が賭博経済に費やされてしまった。
株式市場が経済の中心となってしまい、株価が下がるような政策をとった政府は失敗したとみなされる。これは公共政策や投資判断の誤りにつながる。
ここでオライリーは、ワシントンポストのコラムニスト Steven Pearlstein が2020年に書いた記事から、「FRB(連邦準備銀行)は市場が活況なときには手綱を締めず、市場が下降線となるや、市場は合理的でないと大量の融資を行う。つまりは FRB は株価に床を与えるが、天井は与えない」というくだりを引用する。
中央銀行がやるべきこととして、オライリーが主張するのは以下の3点。
- 最初は小幅に、そして時間をかけて積極的に金利を上げる。それでバブルは崩壊するかもしれないが、投資の裏付けを合理的に判断するようになり、市場は資本の配分をより適切に行えるようになる。
- 金利を上げるかわりに、より大きなインフレ率の上昇を受け入れる手もある。トマ・ピケティが『21世紀の資本』で論じたように、インフレは不平等を減少させる主要な力のひとつだ。
- 賭博経済における株価上昇ではなく、事業経済(operating economy)における中小企業の起業、雇用、収益を目指す。
税制も重要だ。ここでオライリーは、税制に関するアイデアをいくつか紹介している。
- 賭博経済で得た金には、事業経済への投資よりも高い税率を課す。イノベーターのスティーブ・ジョブズとヘッジファンド王のカール・アイカーンが同じように扱われるのはおかしい。
- バイデン大統領が最近提案したように、キャピタルゲインに、労働から得られる所得(普通の所得)と同じ税率を課す。大富豪のウォーレン・バフェットは、彼の秘書よりも低い税率で税金を払っている(マジかよ)。
- マッケンジー・スコットのように、本当にお金を寄付している人にのみ全額の慈善寄付金控除を行う。私立財団など寄付者が管理する機関にお金を預けることで資産を世代間で維持させてはいけない。
- IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に適切に資金提供し、最も貧しい人たちではなく、積極的に租税回避している連中を取り締まる(国税庁長官によると、米国では超富裕層を中心とした「税金泥棒」のせいで年間1兆ドルの損失が発生しているとのこと)。
- 最近 ProPublica の報道で暴露された、超富裕層が高騰するスーパーマネーの資産を担保に借り入れを行い、ほとんど税金を払わないやり口を取り締まる(これは日本でも話題になりましたね)。累進税率には理由があり、超富裕層が抜け道を利用するのは、この制度を馬鹿にしている。
ここでオライリーは、税金の抜け穴をソフトウェア企業にとってのゼロデイ脆弱性にたとえている。つまりは、気づいた時点でさっさと穴をふさぐべきだし、バックドアをシステムに組み込むべきでもないのだ。
そしてオライリーは、税制とソフトウェア企業のアナロジーを敷衍し、Facebook や Google がアルゴリズムを変更しないで、誤報やスパムで市場を混乱させることが許されないように、税制をもっとダイナミックに変えられるようにすべきという本文においてもっともラディカルなアイデアを披露している。Facebook のアルゴリズムに責任を持たせることが可能なんだから、政府にも同じことができるんじゃないか? というわけ。
つまり、我々の社会や市場を設計する「アルゴリズム」は、我々の意図するものになっているか? という問いかけですね。
正直、ケイザイに明るくないワタシにはオライリーの提案の妥当性について偉そうに評価はできないが(そのせいで文意を取り違えているところがあればご指摘ください)、金利を上げるよりはインフレ率の上昇を受け入れるほうが良いかと思いますね。最後の税制に関するアイデアはワタシも大賛成です!
しかし、オライリーのイーロン・マスクに対する評価には、なんともねじれたものを感じる。オライリーは彼のテスラとスペースXを「世界を変える会社」と評価する。しかし、テスラの株価は事業収益に見合ったものではまったくなく、まぎれもなくバブルだし、イーロン・マスクがリッチなのは、企業の PER に合致しない「スーパーマネー」を彼が株式市場から得ているからと断じる。けど、バブルが一概に悪いというのではなく、賭博経済が新製品や生産性向上の原動力になることもあるし、ただし、現在のバブルが合理的な範囲内かというと――と話が蛇行する感がある。
5年以上前に書いた文章だが、ティム・オライリーはリバタリアンであるポール・グレアムの経済的不平等論を斬っていたが、ワタシはグレアムが経済的不平等を論じるのにトマ・ピケティ『21世紀の資本』を引き合いに出さないのはおかしいだろと思ったので(そう書いている)、オライリーがちゃんと『21世紀の資本』を援用していてそうだよな! と思ったものだが、そうした意味でオライリーの視座は一貫していると言えるだろうか。
とはいえ、リバタリアンの最後の拠りどころであるシリコンバレーのスタートアップを支持してきたオライリーが、前回の文章に続いて見せるシリコンバレーの賭博経済に対する強い嫌悪には少しギョッともしてしまう。
そういえば、そろそろピケティの新刊の邦訳も出る頃ですかね。
あと文中引き合いに出される Steven Pearlstein の新刊も、書名からしてオライリーの主張と親和性が高そうだ。しかし、この人の本って邦訳出てないな。