講談社サイエンティフィクの横山さんから『ディープラーニング 学習する機械~ヤン・ルカン、人工知能を語る~』を恵贈いただいた。
著者のヤン・ルカンは、ディープラーニングの第一人者であり、特に畳み込みニューラルネットワークの創始者の一人として知られる、2018年のチューリング賞を受賞した世界的な計算機科学者である。その彼が人工知能、ディープラーニングについて包括的に書いた本が本書である。
また本書の監訳者は松尾豊氏で、ワタシも氏の『人工知能は人間を超えるか』(asin:B00UAAK07S)を読んでいるが、彼が監訳者なら日本語版の内容は問題ないだろうという安心感がある。
本書は書名から一般向けに書かれた AI の概説書で、この分野の世界的な成功者である著者の研究者人生の回顧が主な本かと勝手に思って少し軽い気持ちで読み始めたら、それを最初のほうに一章設けて書いているが(第2章「AIならびに私の小史」)、本領はその後の学習機械、ニューラルネットワーク、ディープラーニングについてずんずん解説していくところにあり、そこでは必然性をもって数式も Python のコードも避けることなく出てきて、事前の見立てよりも読了に時間がかかる読み応えのある本だった。
本書は、著者が終章においてさらっと書いている通りの本である。
適度なハイキングを楽しむというより、険しい山道を駆け足で突き進むようなものだったかと思う。コースの途中には数々の難所があったが、迂回する気はさらさらなかった。なるべく歩きやすうように配慮はしてみたが、この新しい世界になじみの薄い人には、かなりの難関だったかもしれない。(p.369)
これが10万部売れた(著者の本国)フランスはすごいな! とも思うが、読者を甘く見た浅い内容のハウツー本ではなく、本書は一般向けの本ながら、間違いなくこれからも話題の中心となる人工知能分野について、折に触れ再読に耐える本である。
人工知能分野を包括的に解説しながら、当然のようにそこで当然のように自身の研究成果が言及されるところに著者の自負が伝わる。チューリング賞の受賞という、研究者人生の最大のハイライトと言えるトピックについて書く際も、「私の受賞理由はすでに古びた研究によるもので、過去5年間の研究成果はそこに含まれてなかった。(p.293)」と書いてしまう現役意識もチャーミングだ。
著者は、本書の最初で「人工知能は、経済や通信、医療、交通など、あらゆる分野を掌握しつつある。(p.16)」と高らかに宣言しているが、その研究者人生は、いわゆる「AI冬の時代」を乗り越える苦闘とも言える。本書には「タブー視されるニューラルネットワーク」というフレーズがあったりするが、著者たちはニューラルネットワーク研究をバカにされた時代に「ディープラーニング」という新語をひねり出し、なんとか科学コミュニティに居場所を作ってきた話など本当に面白いし(参考:「チューリング賞」が贈られるAI研究の先駆者たちは、“時代遅れ”の研究に固執した異端児だった)、そういう時代にニューラルネットワーク研究を諦めなかった「異端の過激派」として数理工学者の甘利俊一、福島邦彦の名前が挙げられているのも日本の読者には示唆的だろう。
著者は2010年代には成功者として Facebook に迎えられ、Facebook人工知能研究所(FAIR)を立ち上げる。本書を読むと、そのあたりの大企業における AI 研究所の運営と変化についての記述もなかなか読めるものではなく興味深い。そしてまた本書を読むと、この分野の主要研究者はだいたい Facebook か Google に行くんだなと思ってしまう。
著者はマーク・ザッカーバーグが興味ある分野は論文を読み、深く考える人物であることを書いた上で、「何か興味をもったら、いつもそんな風にするらしい。バーチャルリアリティについても同じようにするだろうし、Facebookの民主主義への影響についてもそうするだろう。(p.270)」と少し軽口めいて書いているが、その後まさかここまで Facebook が民主主義の敵、社会の害悪として指弾されることになるとは著者も予想できなかったのだろう。
本書で語られるディープラーニングの成果は、それこそ Facebook のようなもはや巨大プラットフォームがそれなしに機能しないところまで来ていることからも明らかである。一方で、うまく書けないのだが、次の「AI冬の時代」もいずれまた来るのだろうな、ということを思ったりした。
科学コミュニティの一部では、この種の強化学習こそが人間並みのAIを設計するためのカギになると考えられていた。DeepMindの大物のひとりにしてAlphaGoの立役者デイヴィッド・シルヴァーは、「強化学習こそが知能の本質である」と口癖のように言っていた。だが、われわれはその信念に与せず、予言者カサンドラの役割を演じてきた。(p.303)
さて、以下は余談。以前にも書いているが、最近は索引がない本が多く、これは良くない傾向である。電子書籍ならもう索引は必要ないということなのかもしれないが、ワタシが読んでいるのは紙の本なのだ。少しでも出版コストを下げるためなのかもしれないが、出版社のサイトで索引を PDF ファイルで公開してほしいところ。
あと第1章の「偏在するAI」は、「遍在するAI」が正しいのではないか(自分が『デジタル音楽の行方』でやらかした間違いを思い出した)。








![リスペクト ブルーレイ+DVD [Blu-ray] リスペクト ブルーレイ+DVD [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51i4Mt6S2YL._SL500_.jpg)





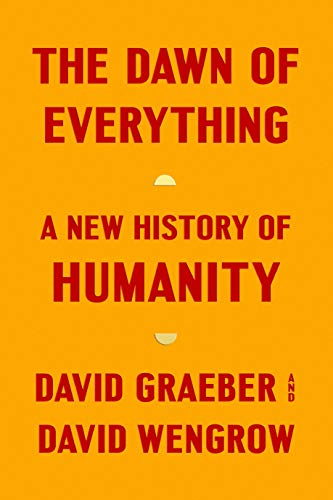










![チェルノブイリ ーCHERNOBYLー ブルーレイ コンプリート・セット(2枚組) [Blu-ray] チェルノブイリ ーCHERNOBYLー ブルーレイ コンプリート・セット(2枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41akYok1hyL._SL500_.jpg)
![ウォッチメン 無修正版 ブルーレイ コンプリート・ボックス (1~9話・3枚組) [Blu-ray] ウォッチメン 無修正版 ブルーレイ コンプリート・ボックス (1~9話・3枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51geyvVfdDL._SL500_.jpg)
![The Office BOX [DVD] The Office BOX [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41JH563TR5L._SL500_.jpg)
![the office クリスマス・スペシャル [DVD] the office クリスマス・スペシャル [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/519MCGZGTTL._SL500_.jpg)
